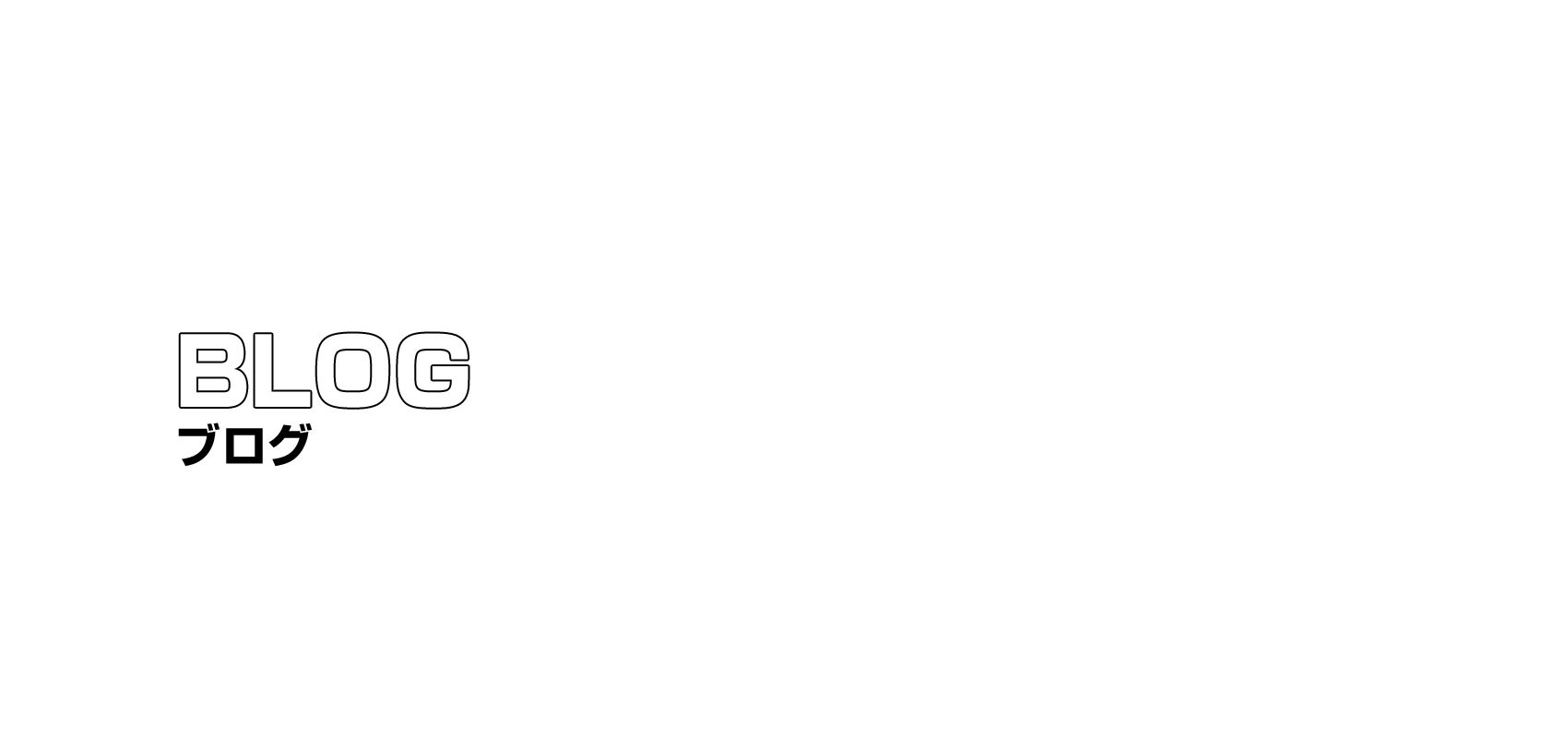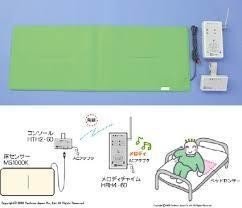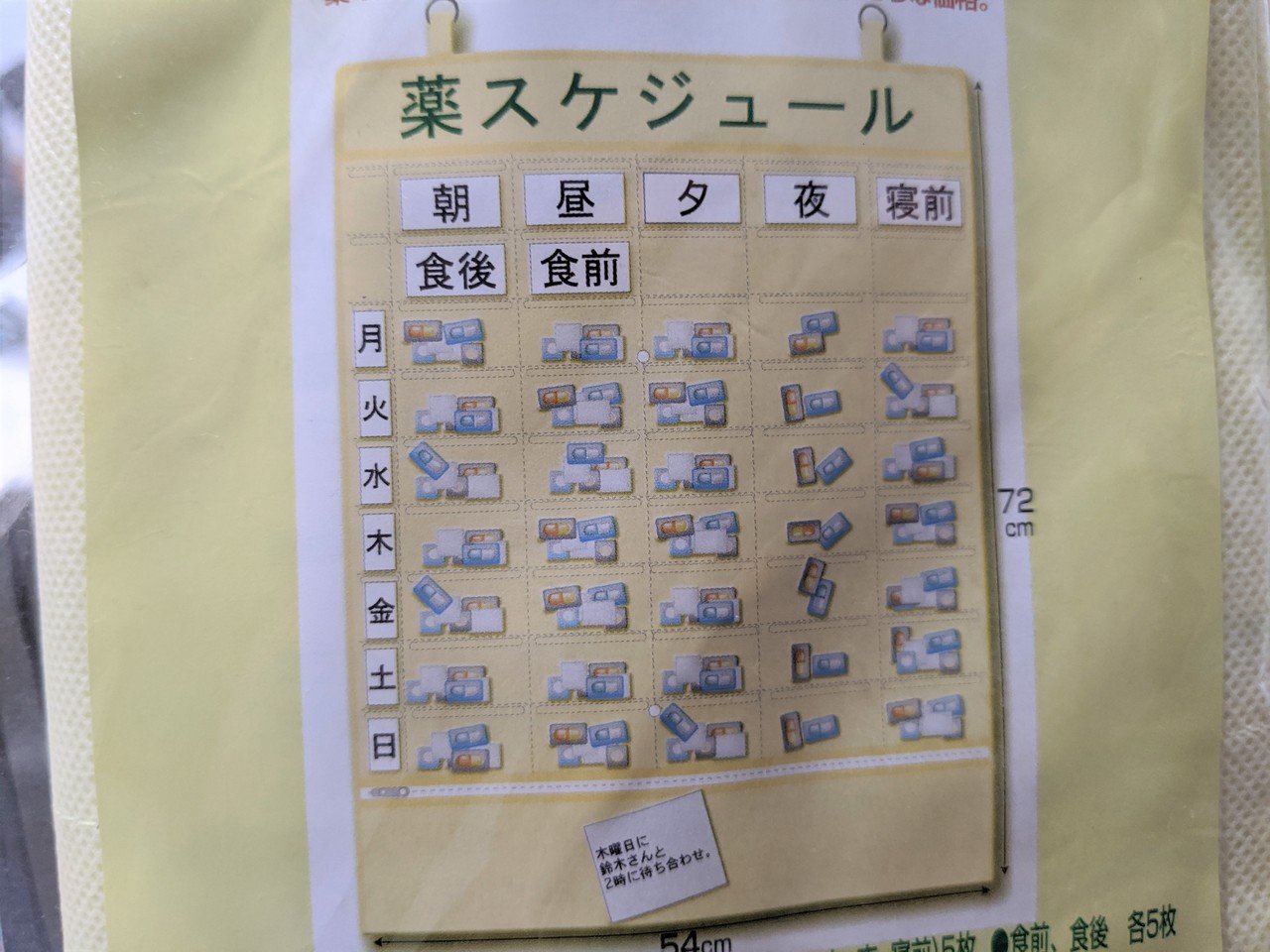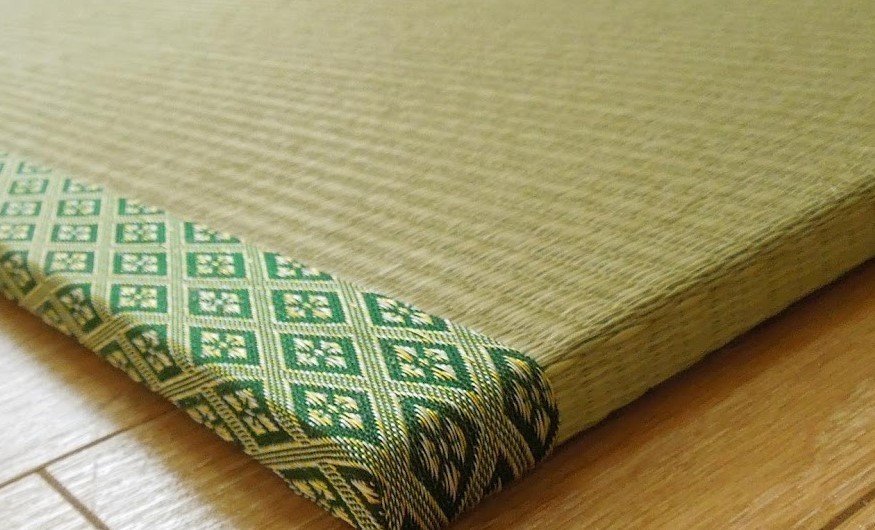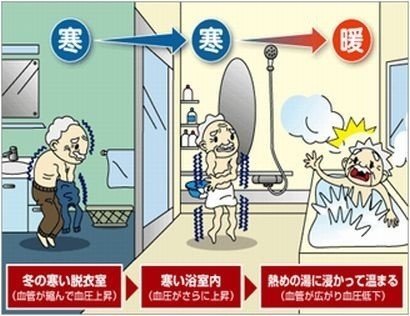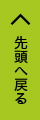福祉用具サービス計画書について
福祉用具サービス計画書は
1、基本情報 2、選定提案 3、利用計画 に分かれています。
1の基本情報は「利用計画」の作成に必要となるアセスメント情報を収集し、整理するための様式です。「利用計画」において福祉用具利用目標の設定や具体的な福祉用具の選定を行うため、この基本情報の様式に様々な情報(身体状況や介護環境、意欲・意向、住環境など)を記載し、利用者の課題やニーズを分析しましょう。
2の選定提案は、2018年から「福祉用具専門相談員が、貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、当該商品の全国平均価格等を利用者に説明することや機能や価格帯の異なる複数の商品を提示すること」が義務となり、商品の特徴や価格、全国平均価格、福祉用具専門相談員が利用者に対して福祉用具を提案した過程を記載したものです。
3の利用計画は「基本情報」に情報収集、記載されたアセスメント内容を踏まえ、「福祉用具貸与の目標を達成するための具体的なサービス内容等」を記載するものです。
【ポイント】「選定提案」は作成後、利用者または家族、ケアマネ―ジャーに内容を説明し、同意を得ます。「利用計画」は作成後、利用者またはその家族に内容を説明し、同意を得て、利用者に対して交付します。できるだけわかりやすい言葉で記載しましょう。
ケアマネ―ジャーはサービス事業所へのサービス計画書を提出求めることが義務化されているので、ケアマネ―ジャーに交付します。